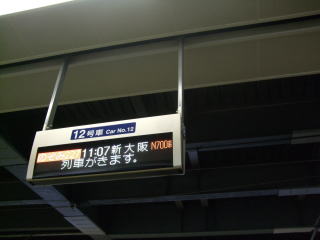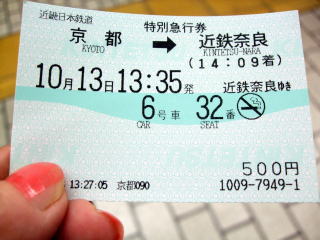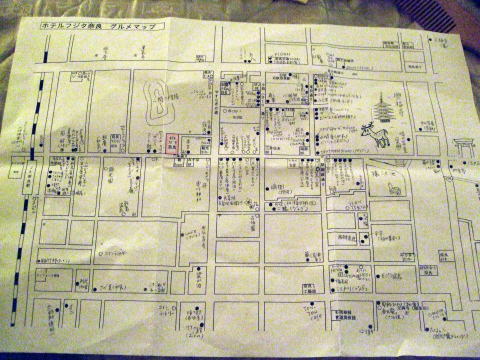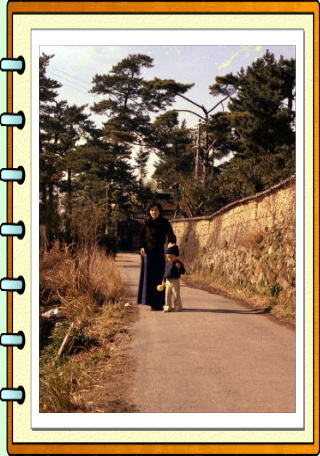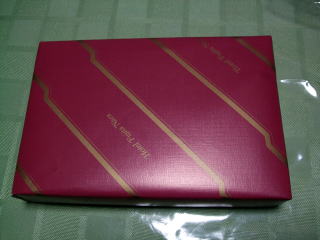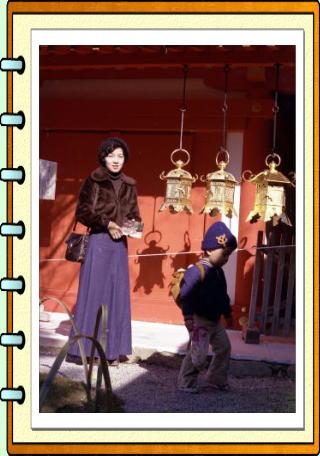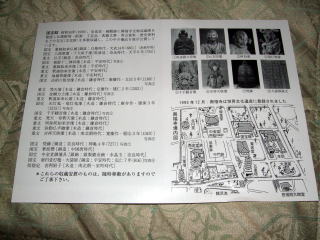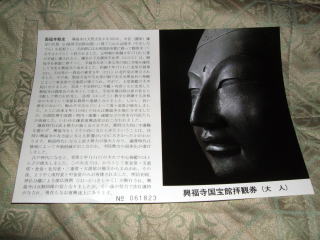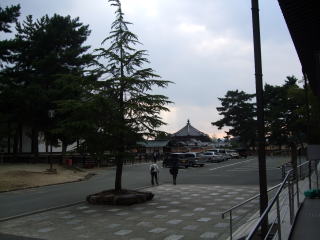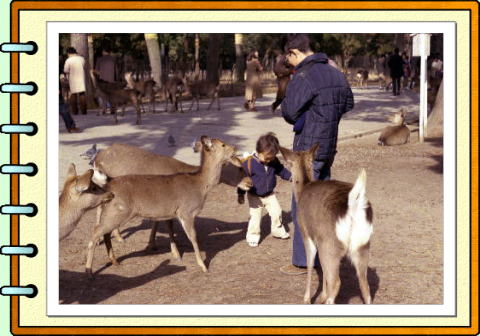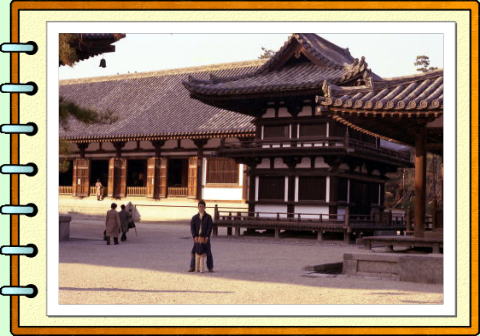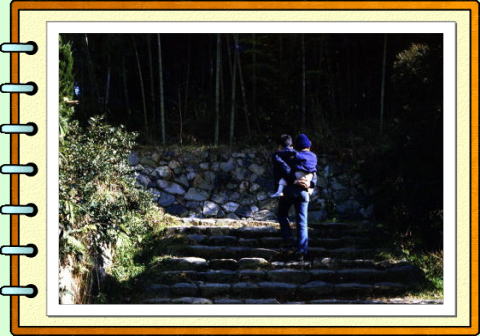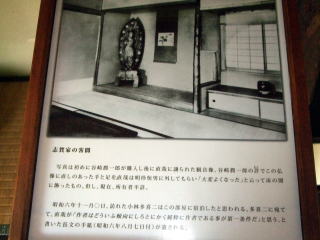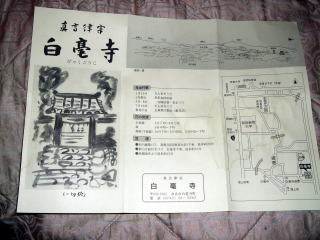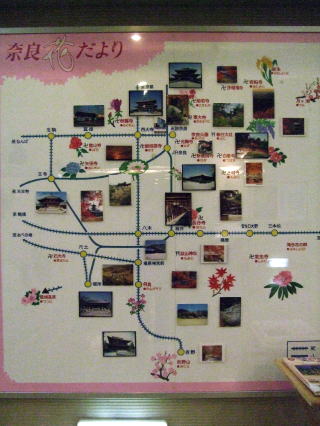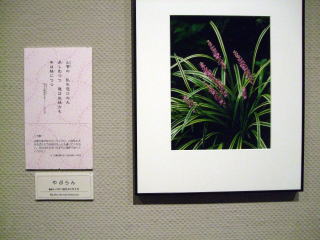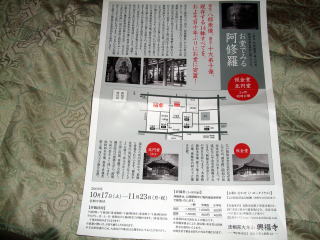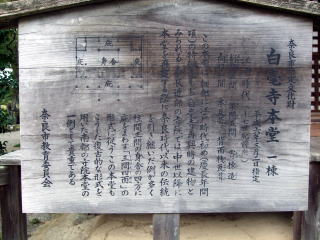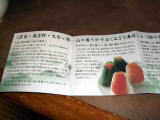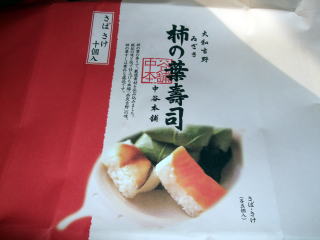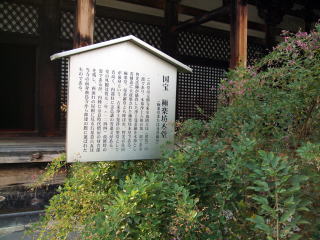�V�q�V�c8�N�Ɂi669�j�������������������߉ގO���������u���邽�߂ɁA�v�l�̋��������A���s�R�Ȃ̎��@�Ɍ��Ă��u�R�Ȏ��v���n�܂�Ƃ���B
���̌����̒n�Ɏ����ڂ��u���⎛�v�Ə̂����B�s�����鋞�ֈڂ����ɋy��ŁA���鋞�����O�����V�̂��̒n�Ɉڂ��u�������v�Ɩ��t�����B
���̑n���̔N��a��3�N�i710�j�Ƃ���B���̌�V�c��c�@�A�܂��������̐l�X�̎�ɂ���Ď��X�ɓ��������Ă�ꐮ�����ꂽ�B
�ޗǎ���ɂ͎l�厛�A��������ɂ͎��厛�̈�ɐ�����ꂽ�B���ɐۊ։Ɠ����k�ƂƂ̊W���[���������߂Ɏ�����ی삳��A
�����͂܂��܂�������ɂȂ����B��������ɂ͏t���Ђ̎������蒆�ɂ����߁A��a����̂���قǂɂȂ����B
���q���������ɂ͖��{�͑�a���Ɏ���u�����A�����������̔C�ɂ��������B���{�ɂ��@���������������]�ˎ���ɂ�21000�Η]�̎�^����ꂽ�B
��������n�߂̐_�������ߥ�p���ʎߥ�Ў���n���Ȃǂŋ������͍r�ꂽ���A���̌�̓w�͂ŕ������A�V�����������̗��j������ł���B
�R����T�O���N�ٓ��@1000�~
�i�씭11:07�@���s���P�R�F�Q�P�@�@�̂��݂Q�Q�V��
���s���@�@13:21�@�@�@����͋��s�����͂��܂���@�@
�i��̉w�ف@�V���X�ٓ��@800�~�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�R�R�N�Ԃ�ɖK���ޗǂł����E�E�E
�g�Q�P�N�P�O���P�R��-15�� �@�@�@�@�@�@�t�W�^�z�e���ޗǂP
�u�꒼�Ɠ@�����ց@�ޗǎs������
2008.10.4 22:58
���C�����u�꒼�Ƃ̋������ޗǎs�i�ޗNJw���j�@�����u�Ö�s�H�v�Œm���镶���A�u�꒼�Ɓi�����P�U�`���a�S�U�N�j����炵���ޗǎs�������̋����i�o�^�L�`�������A
���a�R�N�z�j�ɂ��āA���L�҂̓ޗNJw���i���s�j�͂S���A���Ǝ��g���v�����Ƃ���铖���̎p�ɕ���������j�𖾂炩�ɂ����B���J�������L����\��ŁA
���Ƃ̔��ӎ����`���@����t�ȍ~�ɑS�ʓI�Ɍ��w�ł��������B
�@���Ƃ͏��a�S�`�P�R�N�ɂ��̓@��ɏZ��Ŏ��M�����Ɏ��g�݁A�u�Ö�s�H�v�������������B���ҏ��H���Ă甒���h�̕��l�A��Ƃ炪�W�܂�A
�u�����T�����v�Ƃ��Ăꂽ�B�����͖ؑ��Q�K���ĉ��ז�S�P�O�������[�g���B�����肪������A�m���̌�y����T�����[����������Ă���B
���Ƃ���炵����͋������Ȃ̏h���{�݂ȂǂɎg���A�͗l�ւ����J��Ԃ���Ă����B
�@���J�[���E�����勳���i���z�E���w�j�������̎ʐ^�����Ƃɒ����������ʁA���݂̓@����͂ގ���i���������j�h��̕��͂��Ƃ͂ЂȂт��y�����������Ƃ��m�F�B
�Q�̎q���������d��ǂɑ������݂������Ƃ�A�T�����[���̊����i�������j�̍����Ȃǂ��ύX����Ă��邱�Ƃ����������B�����H���ł́A�ł��邾�������̎p�ɋ߂Â�
�A���Ƃ̎���̕��͋C�𖡂킦��悤�ɂ���Ƃ���

���厛�͐����V�c�̍c���q��e���̕������߂ɁA�_�T�T�N(728)�Ɍ��Ă�ꂽ�����R���i���傤���j���A�V���P�R�N(741)�ɍ����i���������i�����݂傤���j�E
�@�؎��i�ق������j�j�����̏ق�������ꂽ�̂ɔ����A���i���ĂȂ�����a������������O�g�Ƃ���B
�����ēV���P�T�N(743)��Ḏɓ߁i�邵��ȁj�啧�����i������イ�j�̏ق��������A�V���P�V�N(745)��葢���H�����n�܂����B�V���Q�P�N�Ɋ����A
�����ɑ啧�a�̌������i�s���āA�V������S�N(752)�S���ɊJ��i��������j���{��c�܂ꂽ�B
���̏����ȑO����u���̑厛�i�Ђ��̂����ł�j�v�Ƃ������ŒN����Ƃ��Ȃ��Ă��悤�ɂȂ��Ă������A��
�̌�A�����厛�i�ɂ���Đ����Ⓦ���A�u����O�ʑm�[�i����߂��ڂ��j�Ȃǂ����c����A����厛�v�Ƃ��Ă̎�������������ɐ����A
���̖���������W�N(789)�ɔp�~�����܂ő�����ꂽ�B�čt�Q�N(855)�A��n�k�ɂ���đ啧�̓����������A
���̌�C�����ꂽ���A�����̑����̂����肩�玡���S�N(1180)�ɕ��d�t�̌R���ɂ��啧�a���͂��߉����̑唼���Ă��ꂽ�B
�������A�����������������ɂ�A���؋C���ł��������w�����������ɂȂ�A���q����ɂ́A�����̊w�m���y�o�����B�Ƃ��낪�A
�i�\�P�O�N(1567)�Ɏ����ĎO�D�E���i�̗����N��A�킸���Ȍ������c������ƂȂ������A���͐퍑����ɓ���A�����͓�a�������
�A�ȒP�ȏC�������o���Ȃ������B�]�ˎ���ɓ���A�����@���c�����{�ɏ�\���A�������i�Ə��喼�̋��͂āA���\�T�N(1692)�ɑ啧�̊J�ዟ�{���A
��i�U�N(1709)�ɑ啧�a�̗��c���{���s��ꂽ�B���̌�A�����E���a�̓�x�A�啧�a�̑�C�����Ȃ��ꂽ�B
�ȍ~�@�z����͂R�R�N�O�̉��������ʐ^
�s�����`�t
|
���ւ��H�i�y���j�����j
|
�P�C�Q�O�O�~
|
|
�z���f�[�����`�i�y���j�̂݁j
|
�P�C�T�O�O�~
|
|
�����V
|
�P�C�X�O�O�~
|
|
�������H
|
�P�C�X�O�O�~
|
|
�V�n����H
|
�P�C�X�O�O�~
|
|
���ւ��V
|
�Q�C�T�O�O�~
|
|
���ԓ�
|
�R�C�O�O�O�~
|

|
�s�f�B�i�[�t
|
��a�V�V
|
�R�C�W�O�O�~
|
|
�ᑐ���
|
�T�C�T�O�O�~
|
|
���ւ����
|
�V�C�O�O�O�~
|
|
�G�߂̉��
|
�W�C�T�O�O�~
|

���������j�i����������ٔq�ό����j
�@�������͓V�q�V�c�W�N(669)�A���b�i�����j�����̎��@�i�R�鍑�F���S�R�K�j�Ɍ��Ă�ꂽ�R�K���i��܂��Ȃł�j���N���Ƃ��A
�V�����ɂ͑�a�����s�S�Ɉڂ��ĉX�⎛�i���܂₳���ł�j�Ə̂���܂����B�������̘a���R�N�i7 1 0�j�ɓs������ɑJ�����ƁA�����̎q�������s�䓙�i�ӂЂƁj�́A
�X�⎛��V�s�Ɉڂ��ׂ��A���鋞�����O�����V�̒n�Ɏ��n���m�ۂ��Ď������������Ɖ��߂܂����B�a���V�N(714)�ɋ������n������A
�s�䓙�̈�����̗{�V�T�N�i721�j�ɖk�~������������܂����A���̌�A�����V�c��s�䓙�̖��ł�������c�@�̔���ɂ���ē�������d�������Ă��A
�₪�āA���������̑厛�@�ɂȂ�܂����B
�@�ޗǁE��������Ɏ��ρE���e�Ƃ��ɏ[�������������͓������̎����Ƃ��ĉh���A���������ȍ~�͏t���Ђ����x�z���Đ��͂��g�[���A�@���i�ق������j���w����������@���@�̑厛�Ƃ���
��s�����E�̏d���ƂȂ�܂����B�������A�������j�̂Ȃ��ŁA���V�ЂȂǂɂ���ēx�X�������Ď����܂����B�Ƃ��Ɏ����S�N(1180)�̕��͋��������ĖS�����܂������A
���t�@������E���~�E�N�c�E�^�c�Ȃǂ̗L���X�I���������Q�悵���A�����銙�q�������c�������Ȃ��܂����B
���q����͕��m���͂������Ȃ�܂����A���{�͑�a�Ɏ��E��u�����A�����������Ă��̔C�ɓ����点���Ƃ������Ƃ́A
�����̋��������e���ʂɗ^����e���������ɑ傫�����������킩��܂��
�@�퍑����ɂȂ�ƕ��m���͂�����ƂȂ�A�D�L����́A���n�ɂ���Ď��̍팸�������Ȃ��A���@���͂̎�̉����i�s���܂����B
�]�ˎ���ɂȂ�ƁA���ۂQ�N(1717)�̑�Œ��S�����̂قƂ�ǂ��Ď����܂����B���̉Ђł́A���낤���ē������E�d���E�H���E�k�~���E�O�d���E�哒������Ђ���܂ʂ���A
���̌�A�悤�₭��~���ƒ������݂̂��Č�����܂����B
�@���������A�_�������ɂ��p���a�߁i�͂��Ԃ����₭�j���f�s����A�������͊��l�̎p�ƂȂ�܂������A���̌�̓w�͂Ŗ@���쎝���Ȃ���A���݂��Ȃ������r��ɂ���܂��B

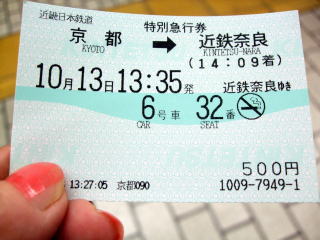



| H21.7.10 |
JTB |
|
34600 |
| H21.7.27 |
�p�X�|�[�g |
800 |
|
|
�i��a�y |
600 |
|
|
�傹��ׂ�370*2 |
740 |
|
|
�낤���� |
1050 |
|
|
�~�j��530*4 |
2121 |
|
|
�[�H |
2800 |
|
| H21.7.28 |
�� |
1575 |
|
|
���y�Y�َq |
1272 |
|
|
�˂���� |
1592 |
|
|
�E���g���}�� |
1600 |
|
|
|
|
|
|
|
14150 |
|
|
|
|
|
| H21.10.13 |
�P�O���P�R���`�P�T���ޗǗ��s��p |
|
|
|
|
|
|
|
�@�T�P�C�O�O�O�~�@�i�s�a�ȊO�i�P�R���`�P�T�����n�Ŏx���j |
|
|
|
�@�V�R�C�O�O�O�~�@�i�s�a�x���\�� |
|
|
|
|
|
|
|
�P�Q�S�C�O�O�O�~�@����p |
|
|
|
|
|
|
�ߓS���}�@13�F35���@�@14�F09�ޗǒ�
�U�P�O�~�{�T�O�O�~�i���}�����j
�@�@�@�@���� �@�@�\��x �@�@���� �@�@�@�{�n��
1 �@�@������ �@�@�@�� �@�@�@���� �@�@�@����
2 �@�@�a�˗� �@�@�@���@�@�@ ���@
�@�@�@���吨�i�����j
3 �@�@�\���� �@�@�@�� �@�@�@�]�@ �@�@�@�����
4 �@�@���ɗ� �@�@�@�\�@�@�@ �B�R �@�@�@�����x�V
5
�@�@���@�@�@ �� �@�@�@���g �@�@�@�ω�
6 �@�@�@�����@�@�@ �߁@�@�@ ���� �@�@�@����
7 �@�@������ �@�@�@�� �@�@�@����
�@�@�@�n��
8 �@�@�k�뗅�@�@�@ �C�@�@�@ �V�� �@�@�@����
9 �@�@���x�� �@�@�@�K �@�@�@��t �@�@�@��t
10 �@�^�ɗ� �@�@�@��
�@�@�@���� �@�@�@����
11 �@�Ɠ��� �@�@�@�N�@�@�@��g �@�@�@������
12 �@������ �@�@�@�q �@�@�@�_�@ �@�@�@�߉ށi�܂��͑ɗ���j
�R�R�N�O�ƕς���Ă��܂���ˁE�E
�����ɂ́A��t�@���i��������E���d���j�A�����E������F�����i���P����̎����I�E�����E���d���j�͕����O�N�i�P�P�W�V�j�ɔR�c������ڂ��ꂽ�Ɖ]���Ă��܂��B�����F�����i�i�O�ށE��ؑ��E���q�����E����j�A�䂢�܈ۖ��������m�����i�O�E��ؑ��B���q�����E����j�A�\��_�������i��ؑ��E���q�����E����j�l�V�������i�O�E��{���E���������E����j��������B
�u�������E�������i����j�v�͋������̎O�̋����̈�ł���A�T�_�O�N�i�V�Q�U�j�n���ł����A�Z�x���Ď��ɑ����A���i��\��N�i�P�S�P�T�j�Č����ꂽ���̂ł��B
�H�����ŁA�˂����Ă��܂��B�@�@�@�@�R�R�N�O�̎ʐ^���Q�l��
�t����Ђ͐_��i�_�Q�N�i768�j�A���鋞�̎��ƍ����̔ɉh���F�肷�邽�߂ɑn�����ꂽ�_�Ђł��B�t���R���n�тɑ�����W�R�̐��[�ɒ������铡�����̎��_���J���Ă��܂�
�B�_�������ɏ���ēޗǂ̒n�ɂ����łɂȂ��Ĉȗ��A���͐_�̎g���Ƃ���Ă��܂��B����10�N�i1998�j�A�Ós�ޗǂ̕������Ƃ��ďt����ЂƏt���R���n�т����E��Y�Ƃ��ēo�^����܂����B
���厛Ḏɓߕ����i�Ƃ��������邵��ȂԂ����j�́A��ʂɁu�ޗǂ̑啧�v�Ƃ��Ēm���镧���ŁA���厛�啧�a�i�����j�̖{���ł���B
�����V�c�̔���œV��17�N�i745�N�j�ɐ��삪�J�n����A�V������4�N�i752�N�j�ɊJ�ዟ�{��i�������悤���A
������̋V���j���s��ꂽ���A�������鑜�͒����E�ߐ��̕�C���͂Ȃ͂������A�����̕����͑���A���A�w�̈ꕔ�ȂǁA
�����ꕔ���c��ɂ����Ȃ��B�u����Ḏɓߕ������v�̖��Œ�������̍���Ɏw�肳��Ă���B
�\��_���́A��t�@����12�̑��ɉ����āA���ꂼ�ꂪ�����12�̎��A12�̌��A�܂���12�̕��p�����Ƃ����B���̂��ߏ\��x���z�������B�܂��A�\��_���ɂ͂��ꂼ��{�n�i���g�O�̖{���̎p�j�̕��E��F�E�����Ȃǂ�����B
�e�_�������ꂼ��7��A���v8��4����ő��鍳�𗦂���Ƃ����B
�o�T�ɂ���Ď�p����ǂ݂��قȂ邪�A�����ł͂����Ƃ���ʓI�Ȃ��̂�������B
���� �ǂ� ���� �J�^�J�i �펚 �{�n��/�� �\��x
�{�����叫�i���������q�j ���т炱��҂� �N���r�[�� ���[ ���ӕ�F �q�_
���ܗ��叫 ���� ���@�W�����@�W���� �T�N ������F �N�_
���闅�叫 �߂��� �~�q�� �L���N ����ɔ@�� �А_
���ꗅ�叫 ���炠��Ă��� �A���f�B�[���A���e�B�� �T �ω���F �K�_
??���叫 ������ �A�j���}�W�� �L���N �@�ӗ֊ω� �C�_
�X�ꗅ�叫 ���炳��Ă��� �V�����f�B���T���e�B�� �^���N ����F ���_
���B���叫�i��ߓV�j ���� �C���h�� �J �n����F �ߐ_
�g�Η��叫 �͂��� �p�W���p�W���� �}�� �����F ���_
�����叫�i��?�����j �܂��� �}�z���K�}�N�� �L���N ��Г����� �\�_
�^�B���叫 ���� �L���i���V���h�D�[�� �A�� ������F �ѐ_
���m���叫 ����Ƃ炵�傤�Ƃ� �`���g�D���`���c�� �o�� ����@�� ���_
��㹗��叫 �т��� �r�B�J���[�� �o�N �߉ޔ@�� ��_
�\��_���� [�ҏW]
����ɂ͊e�\��x�̓������`�ǂ����W����u�����Ƃ������B���{�ł͓ޗǁE�V��t���̓��g��̏\��_�������A�ŌÂ̍�ł���ƂƂ��ɑ��`�I�ɂ��D�ꂽ���̂Ƃ��Ė������B
12�̂̎����A�|�[�Y���͕K���������ꂳ�ꂽ���̂łȂ��A�}���I���F�݂̂���e������ʂ��邱�Ƃ͂قƂ�Ǖs�\�ł���B�\��_�����́A�����ł͑������琧�삳��A�����lj�ɂ���Ⴊ����B�����ł͏\��x�ƌ��ѕt���ĐM����A���{�ɂ�������ɂ�����ɏ\��x�̓�����Ղ����̂������B
���{�ł͓ޗǎ���i8���I�j�̓ޗǁE�V��t�������͂��߁A���������삳��Ă���B�����̏ꍇ�A��t�@����{���Ƃ��镧���ɂ����āA��t�@���̍��E��6�̂��A���邢�͕��d�̑O���ɉ����Ɉ��u�����B�V��t�����̂悤�ɉ~�`�̕��d���͂������Ǝ��͂�Ŕz�u�����ꍇ������A��t�@�����̌��w���������ɏ\��_����\���ꍇ������ȂǁA�\���`�Ԃ͂��܂��܂ł���B
�l�V�����ȂǂƓ��l�A�b�h�𒅂������_�̎p�ŕ\����A12�̂��ꂼ��̌���\��A�|�[�Y�ȂǂŒ��蕪���A�Q���Ƃ��ĕω���������Ⴊ�����B













�@���a34�N(1959)�A���H���E�דa�Ղɋ����������ɂ����݂��Ĉ�ʂɌ��J�B�ʏ̖��u����������فv�Ƃ��āA�L���C�O�ɂ��m���Ă��܂��B���ق͕��������E�G��E�H�|�i�E�T�Е����E�l�Î����E���j�����Ȃǂ̎���i�������j�𑽐��������A���̒��̗D�i��W�����J���Ă��܂��
����@��t�@�������m�����F���P����E�V���P�S�N(685)�n
����@���C�����i�����O���j�i�\���ʐ^�j�E�\���q���m�������F�ޗǎ���E�V���U�N(734)�n
�d���@����m�③�F�ޗǎ���n
����@���\��_�����m�ؑ��F��������n
�d���@��t�@�������m�ؑ��F��������n
�d���@�߉ޔ@�������m�ؑ��F��������n
�d���@�n����F���m�ؑ��F��������n
����@�@���Z�c�����m�ؑ��F���q����F�N�c��E�����T�N(1189)�n
�d���@���V���m�ؑ��F���q����F��c��E���m�Q�N(1202)�n
����@�����͎m���m�ؑ��F���q����n
�d���@�߉ޔ@�������m�ؑ��F���q����n
����@�V���S�E�����S���m�ؑ��F���q����F�N�ٍ�E���ۂR�N(1215)�n
����@���ω����m�ؑ��F���q����n
�d���@���V�E��ߓV���m�ؑ��F���q����n
�d���@����ɔ@�������m�ؑ��F���q����n
�d���@���ӕ����摜�m�ؑ��F���q����n
�d���@�g�˓V�ߑ��m�ؑ��F��k������F���c��E��R�N(1340)�n
���m�����F����������]
����@���������d��[�����F��t�����E�����ʁF�ޗǎ���]
����@��~�����U�E�Αܔ�[�����F��������F�O�m�V�N(816)]�ʐ^�I
���w��@�ɗ��~�q[�ؑ��F��k���`��������]
�@�������̎������u�̂��̂ͤ�����ړ�������܂��̂ł�����������
�@�����A�A�{��A�B���闅���A�C�`���ё��A�D���`���A�E�����S���A�F���ω����A�G�g�˓V�ߑ��A�H�،����A�I�Αܔ�����
����@�����m�����F�ޗǎ���F�_�T�S�N(727)]
����@�،�

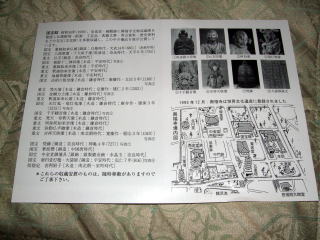
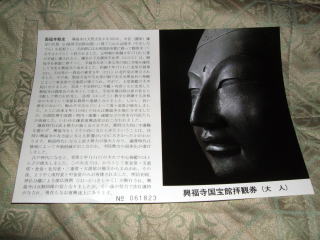




�������E�������i����j
�����̋����ɂ́A��̋�̔肪�����Ă���B�o�l�E�����m�Ԃ͒勝�T�N�i1688�N�j�̏t�ɓ�����K��A�Ӑ^��a��̑��ƑΖʂ����Ƃ����̋���r�B
�w���̏����x�ɂ́A�u���Ӑ^�a�㗈���̎��A�D���V�O�]�x�̓�����̂����܂ЁA��ڂ̂���������������āA�I�Ɍ�ږӁi�����j�������܂ӑ�����q���āv�ƋL���Ă���B
�g�˓V���m�������傤�Ă�ɂ�n�͕����L���̎��_�Ƃ��Đ��h����A
���̋g�˓V���̑O�ŔN���̍ߋƁm���������n������m���n���A���Џ������F��A������g�ˉ��߁m�������傤�����n�̖{���Ƃ����J���Ă��܂�
�ꌩ�Z�d�Ɍ����܂����A���͎O�d�̓���
���B����͊e�w�ɏ֊K�m�������n�ƌ����鏬�������������邽�߂ŁA
���̑召�̉����̏d�Ȃ肪�����I�Ȕ��������������o���u����鉹�y�v�Ƃ������̂Őe���܂�Ă��܂��B
�ē����
�`�F�b�N�C���^�C��13�F00����
�����V�N(1995)
�̍�_��k�Ђ��_�@�Ɍ����S�̂������Ƃ���A���̌X���A���␂�̂���݂Ȃǂ��������A�����ɏC������K�v�����邱�Ƃ����������B�����āA�����P�Q�N(2000)����P�O�N�v��ŋ����̉�̏C�����s�Ȃ����ƂɂȂ���
�S�O���N�Ԃ�ɋ��s�^���[�ɏ��܂���
�s�������Ƀ`�F�b�N���Ă������@���X�@�@��[��
�����₫�̏��a�@�@�S���S�����Ŏ��]�Ԃ͊댯�ł���
�ē����
�@�r�̒��̌�����
���������E���������Ђɂ���ʂ悤�ɂƂ̊肢�������Ƃ����`���J���Ă��܂��B�����ɓ��������肳�ꂽ�Q�S�l�̔�V�͓J��t�ŁA�Ԃ������A�߂�|���A�F��������p�ŁA����n�������ɁA�ݕ����]���Ă��܂��B
1981�N�ɍČ����ꂽ����
�����
�����
�����O�\�O�ӏ���ԎD���B�k�~���ƑɂȂ锪�p�~���B���݂̓��͍]�ˎ���E�������N�i�P�V�W�X�j�ɍČ����ꂽ���̂ŁA����̑��́u����������فv�Ŕq�����Ă����B
�����ɂ悵�@�@�@�����ɐF�̂悤�ł����E�E�E
�@���ɂ����̓ޗnj����@�@�@���Ɓ@�@1976�N1���@
�ē����
�ē����
�������̎O�̋����̈�ł���A�T�_�O�N�i�V�Q�U�j�n���ł����A�Z�x���Ď��ɑ����A���i��\��N�i�P�S�P�T�j�Č����ꂽ���̂ł�
�t�W�^�z�e���ޗ�
���̋��w�܂ŕ����܂��@�@�@�y���͕ۑ��̂��߁H
�g�˓V���摜�@�y����z�@�ޗǎ���
1976�N�ɍČ����ꂽ����
�s�����`�t
�����`�@�`�E�a�i�y���j�����j �P�C�Q�O�O�~
�z���f�[�����`�i�y���j�̂݁j �P�C�T�O�O�~
�t���[�� �Q�C�O�O�O�~
�X�e�[�L�����` �Q�C�O�O�O�~
�\���C�� �R�C�O�O�O�~
�s�f�B�i�[�t
�_���W���� �S�C�O�O�O�~
�X�e�[�L�f�B�i�[ �T�C�O�O�O�~
���r�G�[���R�[�X �S�C�O�O�O�~
�A�[���A�R�[�X �U�C�O�O�O�~
�G�߂̖��o �V�C�O�O�O�~
���X�g�����@�V�F�[���_���W����
�ē����
���N���͂��łɍ炫�I����Ă��܂���
�@�@�@�@�@�@�z�g�g�M�X�����ꂢ
��t���i�₭�����j�́A�ޗnj��ޗǎs���m�����ɏ��݂��鎛�@�ł���A�������ƂƂ��ɖ@���@�̑�{�R�ł���B��s���厛�̂ЂƂɐ�������B�{���͖�t�@���A�J��i�n���ҁj�͓V���V�c�ł���B1998�N�ɌÓs�ޗǂ̕������̈ꕔ�Ƃ��āA���l�X�R��萢�E��Y�ɓo�^����Ă���B���E�ǎ�͎R�c�@���ł���i2009�N8��?�j�B
�@�@��t���Č��̗��j
�@1976�i��.51�j�@�@�������c
�@1981�i��.56�j�@�@�������c
�@1984�i��.59�j�@�@���嗎�c
�@1991�i��.03�j�@�@�����O���@�������c
�@1998�i��.10�j�@�@���E������Y�ɓo�^�����
�@2000�i��.12�j�@�@��A���A���R��v�攌�ɂ��u�哂����lj�v��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����O���@�����̕lj�a�Ɍ��[�����
�@2003�i��.15�j�@�@��u�����c
�c�̂���ɋ�����Ȃ��ā@�@�@���肵�܂�
��~���i���������j
�ē����
�ē��͂���܂����E�E�E�E�E��t���́H�H�H
��芷���ā@���̋��܂Ł@�Q�T�O�~
���w�̏C�w���s�Ŕ��܂���
�@�@�@�������ق��܂�����܂���
�r�Ɍd�����ʂ��Ă��܂���ł���
�@�@
ꡂ������ɋ������̌d���������܂�
�`�̗t���i�ŃG�l���M�[���^����
�ē����
�I�[�h�u���@�@�T�[�����@�e���[�k
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}���l�@��
�V�K
�z�[���@�R�S�ȁ@�@�J�E���^�[�@�P�O�ȁ@�@���@�X�Q�ȁ@������i�����~�P�O�{�P�Q�{�V�O�j
�����` �P�P�F�R�O�`�P�S�F�O�O�@�f�B�i�[
�P�V�F�O�O�`�Q�P�F�O�O
�����������Ă��܂����A�����ł�
�Ԃ̂����A������
��x�݂��ā@�@�Ăы��낵�������K�i������܂�
���厛�͎ʐ^�B�e��������Ă��܂��@�@
�d���i����j
�@�����T�P���[�g���B�Ó��Ƃ��ẮA���s�̓����̌d���T�T���[�g���Ɏ��������œV����N�i�V�R�O�j�����s�䓙�̖��E�����c�@�̔���Ō����B
�����̌����́A��������̉��i�\�O�N�i�P�S�Q�U�j�Ɍ��Ă�ꂽ�Z�x�ڂ̎�������̌����Ȃ���A�S�̂ɑn��������`���鏃�a�l�̖����z�ł���
1977�N�܂ł͢�������Ɋy����Ə̂��Ă����������i�������j�́A�y�Ós�ޗǂ̕������z�Ƃ��Đ��E��Y�ɓo�^����Ă��܂��B
�����ޗǎs�̎ŐV�����ɂ��錳�����Ƃ������@������܂����A���X�͈�̎��@�ł������A���E��Y�ɓo�^����Ă���̂͒��@���̌������ł��B
�Ԃ̂����Ƃ��Ă�邱�̎��@�́A���{�ŌÂ̂�����718�N�ɓޗǂɈڂ��ꂽ���̂ł��B
�܂�ŃA�j���̈�x����ɏo�Ă���悤�ȑf�p�ȕ��͋C�Y�������ŁA�l�G��ʂ��Ĕ������Ԃ��炫����邨���ł��B�G�߂��Ƃ̉Ԃ́A3�����{�ɒցA
����{�ɂ͍��A6����{����9���̉��{�ɂ����Ă͋j�[���炫�A9���̉��{����͔��������ɂȂ�܂��B
�X�e�[�L�f�B�i�[ �T�C�O�O�O�~
���|�i�тႭ�����j�Ƃ́A���̔��Ԃɂ����ď�Ɍ��������Ƃ��������т̂��Ƃ������B
1976�N1���@�@
�@�@�@�@����Ȃ������̂ł��˂��E�E�E
��s����_�У�͐V��t���Ɨאڂ�
�Ă���K���ƐԂ��������ڗ����V
��t������ɖڂɓ���܂��B
�@���_�Ђ͑哯���N(806)�ɐV��t
���̒���Ƃ��Ċ������ꂽ�Ɠ`����
��Ă���܂�
�u�꒼�Ɠ@
��a�V�V
�R�C�W�O�O�~
�`�F�b�N�C�����ς܂��@�����^�T�C�N���ł��ł����@�@�@�R�G�R�O�o��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���500�~
���X�X�@�@�P�O���O�Ȃ̂ł܂��J�X�O
�̂͂���Ȃɑ�ς������Ƃ͎v���܂���ł���
���̂��o�}���@�@�@�@�c�̂�����吨���܂�
�P�X�X�W�N�P�Q���@�������͐��E������Y�ɓo�^����܂����B
������
�|�M�͂��̂܂܁@�@���͋C����܂�
�Ԃ̎��Ƃ��Ă��m���锒�|���̋����ɂ́A��������̒ւ┋���A�����Ă���B
���ł�����������ڐA�����Ƃ����u�ܐF�ցv�i���V�R�L�O���w��j�́A���厛�J�R���́u�Ђ��ڂ��v�`�����́u�U��ցv�ƂƂ��ɎO���ւƌď̂���Ă���B
���t�W�ɂ��o�ꂷ�鍂�~�i�����܂ǁj�R�̐��[�Ɉʒu���锒�|����������́A�ޗǂ̊X���݂����]�ł��A�ւȂǂ̉Ԃ̎��Ƃ��Ă��m����B
�����腖����y�т����ő��̕����i������d���j���g��␂ނ悤�Ȕ��͂������ĕK���B
��s���_��
�z�e���i��j����E�����꒼�����Q���@�ɂ₩�ȏ��
�i�q�E�ߓS�ޗǂ�������ĂT���B
���E������Y�ł��鋻������t����Ђւ��k�������ŁA
��ϕ֗��ȏꏊ�Ɉʒu���Ă��܂��B
���͋C�͐̂̂܂��@�@�f�W���u�E�E�E�E
�ē����
�`�F�b�N�A�E�g�@�@11�F00
���n�E�����t�@�@�P�P�O�O�~
2003�N�i����15�N�j3��21������
�T�����[����
�ē��̕��ɎB���Ē����܂���
����������ٔq�ό��ɋL�ڂ̐�������B
�����⓹�@�@�����Ɍ������̒����܂ő����܂��B