有形文化財(彫刻)
有形文化財(絵画)
有形文化財(工芸品)
天然記念物
無形民俗文化財
史跡
有形文化財(建造物)
有形文化財(彫刻)
加藤楸邨句碑
落葉松はいつめざめても雪降りをり
加藤知世子句碑
寄るや冷えすさるやほのと夢たかへ
加藤楸邨句碑
しづかなる力満ちゆきはたはたとぶ
河口慧海師碑
慧海の13回忌に際して門弟・親戚等が建立
 |
鐘楼
 |
 |
 |
緑濃い浄真寺には、東京都指定天然記念物のイチョウ、カヤがある。また、かつてはサギソウ園(世田谷区の花)があり、
区民に親しまれていたが、駐車場拡大により取りつぶされ、今は本堂脇の片隅に僅かに残るのみとなってしまった。
 |
 |
 |
2014年-34年まで大修繕
浄真寺(じょうしんじ)は東京都世田谷区奥沢七丁目にある、浄土宗の寺である。山号は「九品山」。
「九品仏」(くほんぶつ)とは、
一義的には、後述のとおり同寺に安置されている9体の阿弥陀如来像のことであるが
一般には同寺の通称となっている。
転じて、同寺の周辺の地区を指す場合にも用いられる。
九品仏駅
11:08に乗ります
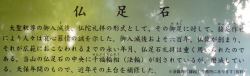 |
10:27 参道に入ります
駅から徒歩1分で参道入口です
10:57 仁王門を通って
12月8日
九品仏
M・Y
仏足石
国鉄大井工場跡地
うまい鮨勘
11:49 ランチセット 1200
JR東日本アプリ」を使うと
アプリ内のメニュー「列車に乗る」から、「列車走行位置(山手線トレインネット)」を開き。
そうすると、山手線内回り・外回りにおける現在の列車走行位置が表示されます。
E235系を使用した列車は専用のアイコンで表示されているため、自分がいる山手線の駅で、
あと列車を何本待てば新型のE235系がやって来るかが、すぐにわかるのです。
ここは何でしたっけ
しばらく見ないうちに・・
11:30大井町に到着
10:06 新しい山手線 初めて見ました
11:00 約30分の見物でした
本堂から眺めた景色
斜めのベンチ
970円
|
|
駅舎は上り線と下り線の間にあります
10:27 旗の台で乗り換えて 九品仏駅に到着
案内より
10:11発急行に乗ります