


10:20





駅前は相変わらず混雑
昔の東京駅は思い出せませんが・・・

12:18
新丸ビルからの見物を終え





日比谷通りを渡って









皇居見学へ


今月2度目の東京駅 未だ混雑
9:31
H24年10月22日
皇居見学
MY
青物横丁
↓9:08
↓京急本線
↓9:12
品川
↓9:17
↓9:28
東京
出発日:2012/10/22
所要時間:22分
片道金額:290円

石垣と松 10:23





桔梗門の屋根 鯱
桔梗門から入ります
9:48 簡単に受付を済ませ










10:17
島津家の紋章が3個


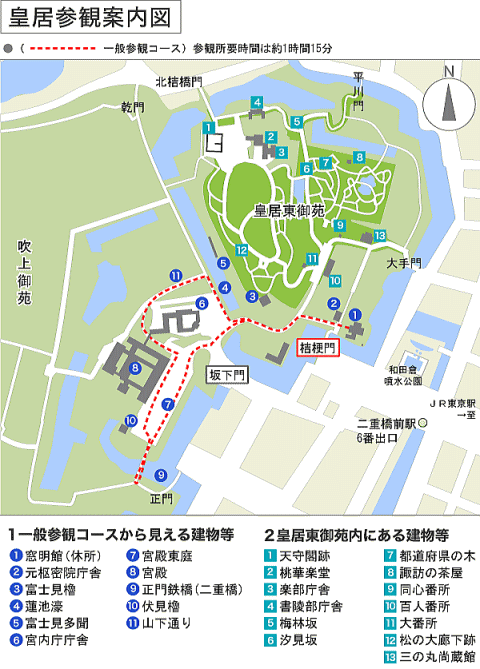











11:23内堀通り
俗世間がそこに 11:20
11:21 タワー方面

ぞろぞろと
美しい松も見納め

富士見櫓大きく見えて11:10

| 蓮池濠は,名前のとおり,夏季には多くの大輪の蓮の花が見られます。 |

正門鉄橋から伏見櫓を望む 手前のランプは正門鉄橋のもの。
建物で江戸城の昔の面影を伝えるものは、わずかに残る櫓。
この二重櫓は、当時の西の丸の殿舎の西南隅に建てられたもので、左右には、かなり大きな多聞も残っています。
江戸城築城の第二期(三代将軍家光の時)の寛永五年(1628年)に京都伏見城から移築したものと伝えられています。
別名で「月見櫓」とも呼ばれており、皇居で最も美しい櫓と言われ櫓の高さ約13.4メートルあります。
石垣も櫓も堅牢に出来ており関東大震災でも崩れませんでした。
この伏見櫓の奥に、両陛下のお住まいの御所などがある「吹上御苑」。
宮殿東庭の大刈り込み
「長和殿」の左奥は「宮殿の南庭」で広い地形と芝生を利用して、大刈り込みの下は小川が流れていて流れを主としたお庭
小山のように見える二つの刈り込みは「南庭の大刈り込み」でいろいろな樹木が合わさって出来た刈り込みです。
大変大きなもので高いところでは6mもあります。
刈り込みは職人が入り込んで、すべて手バサミで刈り込みをしています。
昭和の初期にこの宮内庁庁舎で1度だけ一般参賀がおこなわれました。
正面玄関の赤いジュウタンの上の2階の所に平らな屋根がありますが、そこに天皇皇后両陛下が
お立ちなりお手を振られたとのことです

通称二重橋へ

消防車も待機?
見学の注意と案内ビデオを観て
今日は少なめ約150名参加
10:28


9:41 9時50分までに集合
9:42 もうすぐ集合場所 桔梗門
9:40 特別史跡江戸城跡
日比谷通り 9:37
鉄橋から正門石橋(通称眼鏡橋)を望む(
資料写真より




実に見事な石垣 10:39


皇居でお土産



宮内庁庁舎を行きと逆回りして 出発地点に戻ります 11:07







肉


目の保養と気持ちの安らぎを胸に



川鵜?


戻って来ました 11:16
お疲れ様でした 11;18


ガソリンスタンドも営業中?
最後の坂を下りて 11:16

宮殿横 宮内庁の裏側を行きます



伏見櫓の鯱

皇居正門の元の名前は西の丸大手門でしたが、明治21年(1888年)の 明治宮殿造営のとき、この門のすぐ前にあった高麗門を撤去し、
名称も 皇居正門と改めました。 建造は3代将軍徳川家光公の時代と推定されています。
「皇居正門石橋」は江戸時代のときは土で出来た「土橋」でしたが、明治20年12月に現在のようなめがね型をした
美しいアーチを描いた石橋になっています

160mの長和殿
中の廊下は100m
江戸城旧本丸の東南隅に位置する「富士見櫓」で、品川の海や富士山をご覧になったといわれています。
現存の三重櫓は、万治2年(1659年)の再建で、江戸城本丸の遺構として貴重な存在といわれています。
天守閣が明暦3年(1657年)の大火で焼失した後は復旧されなかったので、
富士見櫓が天守閣に代用されたと伝えられています。
どこから見ても同じ形にみえるために、俗に八方正面の櫓とも呼ばれ、特に石垣上にせり出している
石落し仕掛けのある南面の屋根が描く曲線はとても優美です。
桔梗門は皇居参観者や勤労奉仕者などが出入りする門で、「内桜田門」と呼ばれていますが、昔この門の瓦に太田道灌の家紋が(桔梗)ついていたことから桔梗門と呼ばれるようになったとも伝えられています。

宮殿で一番長い建物が「長和殿」で長さが160mあり、中の廊下の長さは100mあります。
この場所で、新年1月2日と天皇誕生日の12月23日の年2回、天皇皇后両陛下と皇族方が長和殿中央バルコニーに
お出ましになり国民からのお祝いを直接お受けになります。その際,天皇陛下からのお言葉があります。
「長和殿」の前の広場が「宮殿東庭」で、広さが約4500坪あり、一般参賀などの多いときには約2万人が一度に参賀できます。
足元の石畳は四国香川県産の安山岩が使用されており、大変水はけの良い石で、足に優しい石です。




前回テラスに出られなかったので
やはり今日は混んでます

あわてて入ってしまったので・・・・・
タイ料理でしたか・・・
サラダ 辛い
新丸ビルに来ました 11:30 混む前にどこかに入らねば
11:24

桔梗門の鉄扉
蓮根は取らずにそのまま肥料にするそうです
11:06

おっと 事件か 猛スピードで走り去りましたよ




モミジの木



ビルより低い桜田二重櫓 宮殿まで戻ります
10:56


10:13 見学開始
番号は見学順を優先

9:49 桔梗門
正式名称は内桜田門
お城だっ
鶏
お昼はどこで?
11:26
もみじ山の下の通り だそうです
11;00